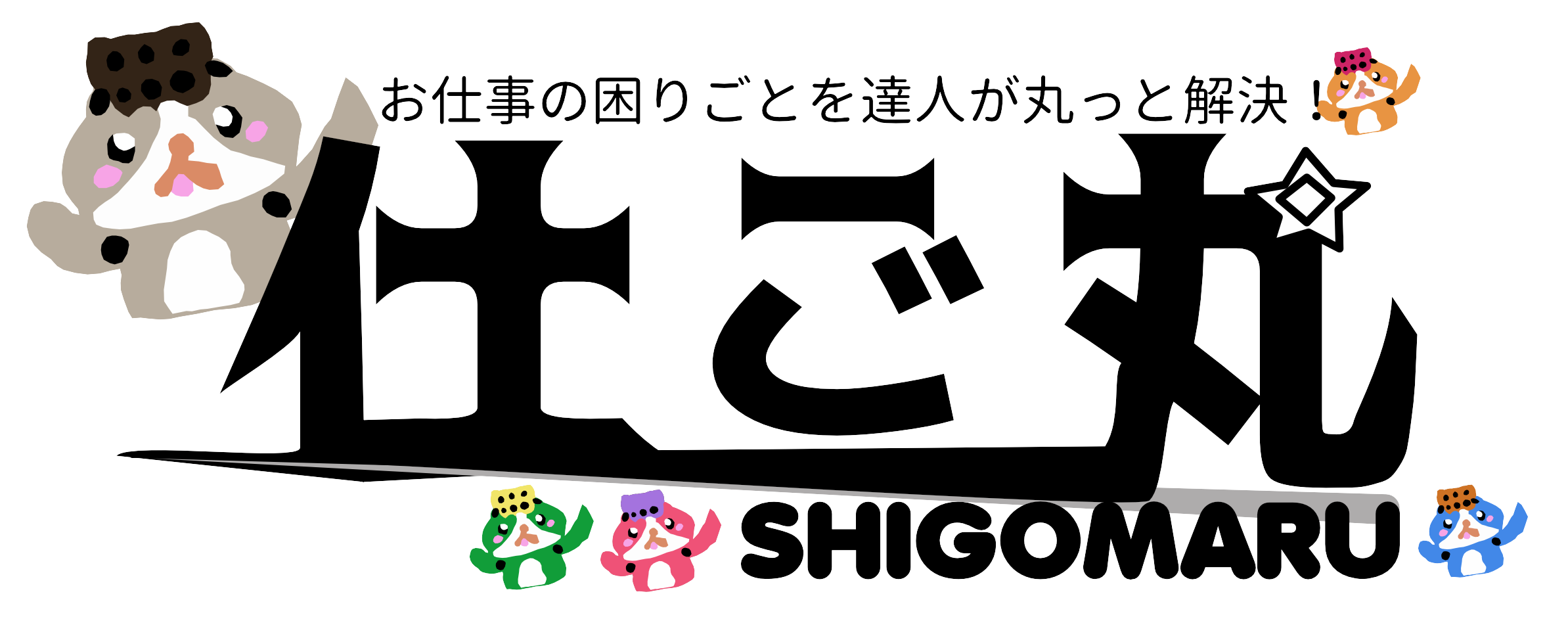秘書という職務は、担当する上司によって求められる役割が違う事が特色だと思います。
担当替えするだけで今までのやり方が通用しなかったりすることが多く、混乱することも少なくないです。
場合によっては混乱から抜け出せず、ストレス過多となってしまうこともあります。
今回は、ただ振り回されるだけにならないよう、そもそも秘書に求められる役割とは、について書いていきたいと思います。
1、求められる役割

まず、秘書は相手ありきでの職務であり、仕事内容も求められる役割も流動的だという事を念頭に置いておくと良いです。
極端に言うと秘書の「意思」は必要ありません。上司の「意思」で動くことが秘書の仕事だと私は思っています。
ここを混同してしまうと、「自分だったら・・・」という感情に振り回されることになり、混乱してストレス抱え込んでしまったり、業務もうまく回らなくなってしまうかもしれません。
例えば、日常的に忙しい上司とメールでの業務確認の際、気配りのつもりで上司が返信しやすいよう選択肢を提示し、イエスノーの回答をお願いするとします。
ですが、これも人によっては出すぎた内容だと不快に取られる方もいらっしゃいます。
イエスかノーで返事するかどうかは自分が決めることで、メールで秘書に指示されることではないと、ヘソを曲げる方もいらっしゃるのです。
相手に合わせて、仕事の効率を重視する方へは無駄を省きシンプルに、礼儀を大事にする方へはコミュニケーションと丁寧さを十分に表現するようにしましょう。
秘書は彼らの仕事が滞りなく進められるようにサポートする仕事です。
相手が何を求めているか。相手に寄り添い慮ること。
自分がなりたい秘書像ではなく、相手が求める秘書像を見極めて柔軟に対応しましょう。
2、観察力

上司の意思を知るためには、日常のコミュニケーションや多角的・客観的な観察から、情報を得る方法があります。
主観で物事をとらえると、自分の思い込みや先入観にとらわれてしまい、正しい判断をすることができません。
だからと言って周囲からの評判を鵜吞みにすることもダメです。その人が受けた一方的な視点だからです。
先入観を持たず、自分を信じて、総合的かつフラットに観察してみてください。
上司が何をモットーにしているか。性格、ルーティン等。座右の銘なども直接聞いてみてもいいかもしれませんね。思考パターンがわかりやすくなります。
観察力がつくことで相手が求めているものや小さな変化にも気づくようになり、本当の意味での気配りや気遣いへつながります。
上司の中には「雑談相手役」を求める人がよくいます。
その方たちにとっては、雑談をすることで頭の中を切り替えたり、別の発想を思いついたり、雑談がいわゆる仕事のルーティンとなっていたりするのです。
雑多なジャンルの会話の中から上司のプライベート状況や趣味趣向も拾えますので、スケジュール調整の上でも、今の時期は予定を詰めすぎない方が良さそうだなとか、これは最優先にしてほしい予定だなとか、察することもできるようになります。
また、相性が良くないと思っていた相手でも距離を縮めることができます。
例えば、少し気難しくてこだわりが強い上司を担当したことがあります。
手土産の一つ一つにも趣向があり、今日はAのお店の○○を、明日はBのお店の○○を買いに行ってほしい。と頼まれることもしょっちゅうでした。
時間もなく何とかやりくりして用意していましたが、ある日上司との雑談中にポロっと「時間が足りないです」と冗談半分で言っていたら、可能なときは自分でお店へ受取りに行けるから大丈夫だよと言っていただき、負担が軽くなりました。
普段のコミュニケーションから感じ取って下さった気遣いなのだと思います。
労ってもらえると、秘書としてもやる気につながりますので、日常のコミュニケーションは大切だなと思いました。
観察力、雑談力によって、仕事へも信頼関係にもプラスになる対応へつなげていきましょう。
3、柔軟性

先ほど、相性について少し触れましたが、秘書は上司と特殊な関係になるので相性が良くないと、そのままストレスにつながり、効率が下がります。
私は数社でいろいろな方を担当してきましたが、幸いにも皆さんにとても良くしていただき、退社した今でも交流があります。結果として、相性が悪かったと思う上司はいない気がします。結果として、ですので、当初は合わないと感じた方が半分くらいいたような気もします。
ここまで読まれて気づかれた方もいらっしゃると思いますが、私の記憶力はあまり良くないのです。深く考えることも苦手です。
実は、これが柔軟性に繋がっていたのかもしれないと、最近思うようになりました。
殆どの方が秘書業務に求めることは、柔軟性とスピード力だと思います。
秘書が先の予想をして段取りを組むことと、余計な考えを挟むことは違います。
難しく考えない。何を相手が求めているかをシンプルに捉えて、状況に応じた対応をすることで、周囲からの信頼度もあげていきましょう。